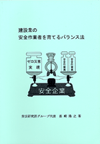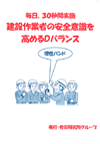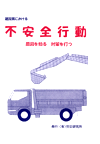下記【図1】は、一つの建設工事を体系的に表したものです。元請会社では、その工事金額に応じて労災保険に加入します。すると、その工事に携わる全ての労働者は、現場で被災したとしても、この元請会社で加入の労災保険で救済されるようになっています。しかし、現場で働いている人全てが労働者とは限りません。一人親方や中小事業主といった労災保険の対象とならない方も数多く働いているのが現実です。
国では、こういった労災保険を使うことができない一人親方や中小事業主の方を救済する目的で、労災保険特別加入制度を設けています。この制度に加入することにより、労働者と同等の手厚い補償を国の制度として受けることができるようになります。
国の労災保険制度は、労働者とその家族の生活基盤補償として、その充実した補償内容は他に類を見ません。そして、労災保険特別加入制度は、労災保険で救済されない人達を労働者と等しく救済できる特別な制度なのです。
私たちは、“国の労災保険制度を基盤とした『安定した労災補償制度』づくり”のお手伝いをいたします。
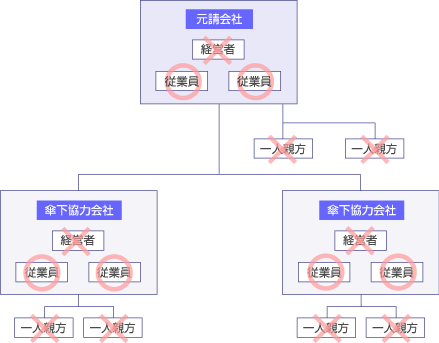
【 図 1 】
会社の労災補償制度の一環として労災特別加入制度を導入したい
建設業の作業現場では、様々な職種に様々な企業が混在して仕事をしています。更に、そこで働く人たちの労務形態も様々であり、中には労災保険の対象とならない一人親方や中小事業主の方も混在して働いているのが現実です(図1参照)。元請会社では、こういった建設業の持つ複雑な態様を考慮して労災補償制度を考えていかなくてはなりません。
労災保険制度は、働く人たちとその家族の基礎的生活を補償してくれる非常に優れた補償制度であることは言うまでもなく、建設現場で働く“全ての人たち”がこの労災保険制度によって救済されることが望ましく、理想的です。
労災保険制度の対象とならない一人親方や中小事業主の方は、労災保険に特別加入することにより、労働者と同等の補償を国の制度として受けることができます。これにより、建設現場で働く“全ての人たち”の安定した補償基盤づくりができるのです。このような観点から、会社の労災補償制度に労災保険特別加入制度を組み入れるということは、非常に大きな意味を持つのです。
傘下の一人親方を一括加入したい
イ、元請会社から、傘下の一人親方の方の労災特別加入を求められて
いる企業の皆様へ
元請となるゼネコンやハウスメーカーでは、“労災特別加入していない一人親方などは現場に入場させない”のが一般的になっています。更に、傘下の一人親方について一括加入管理を求める元請会社もあります。しかしながら、一人親方を抱える企業の皆様からは“どこで、どうやって加入すればよいのかわからない”といったご意見もいただきます。
労災研究所グループでは、労災保険特別加入制度にあたっての様々な疑問について、貴社に代わって対象者に具体的にわかり易くご説明いたします。“加入が必要となる対象者”、“加入方法”や“補償内容”、“事故の際の対応”などについて、制度が適正且つスムーズに運用できるよう導入から運用までをサポートいたします。また、労災研究所グループでは、加入手続から入金管理までを一元的に管理いたします。傘下の一人親方を一括加入する場合には、今まで労務担当者が行っていた複雑な加入管理を行う必要が無く、管理業務上のメリットを最大限に生かすことができます。
ロ、既に労災特別加入制度を導入しているが、その運用・管理面でお悩み
の企業の皆様へ
貴社傘下の特別加入者について、加入管理をしていく上での問題点を具体的に見てみましょう。
- 特別加入の保険期間は、1年です。よって、特別加入であるか否かの確認作業は、労災保険の更新時期に合わせて“毎年”行う必要があります。更にこの確認作業は、各加入者への“個別対応”となるため、事務的にも大変な時間と労力が必要となります。
- 特別加入証明として提出される書類は、多種多様です。それぞれが特別加入する団体によって、発行される書類が異なる上、民間保険証券を提出してくる人もいます。多種多様の提出種類を一つ一つ精査して、労災保険特別加入者か否かを確実に判断しなければなりません。これには専門的な知識や経験が必要です。
- 特別加入者が、保険期間の中途で加入団体を退会した場合、その時点で労災保険も未加入の状態となります。この事実を知らないまま本人を使い続け、万が一被災したような場合には、貴社にとって非常に大きなリスクとなります。しかしながら、“労災保険の非適用者となった”という本人にとっての負の情報は、使用する会社にはなかなか聞こえてこないのが現実で、管理上の大きな問題となっています。
労災研究所グループによる一括加入は、こういった様々な管理上の問題を解決します。加入から退会までの一連の管理について、当グループが一元的に行い、貴社へのフィードバックを行っています。

貴社では、毎年の煩雑な加入確認作業が不要となるばかりか、保険期間中途で退会し、労災保険が使えなくなった人たちを確実に排除することが可能です。
傘下の一人親方について、一括して特別加入することは、管理業務上非常に大きなメリットがあるのです。
全国の事業所で、同一条件で加入し、加入状況を管理したい
特別加入を扱う団体は、加入対象地域が限定されています。すなわち、対象地域以外で働く一人親方は、特別加入できません。したがって、全国で営業展開している企業や企業グループの傘下で働く一人親方の方が特別加入をする場合、加入団体が異なることから地域によって保険料等の加入条件に格差が発生してしまいます。
労災研究所グループでは、
※全国40都道府県で働く一人親方の方が特別加入できます。全国で営業展開している企業や企業グループの傘下で働く全ての一人親方の方について、同一条件でこの制度をご利用いただけます。更に、今までのような煩雑な管理業務に時間と手間をかけることなく、県単位や支店・営業所単位といった地域別管理も含めて、一元的な管理が実現します。労災保険特別加入制度は、加入者が万が一働けなくなった時、本人とその家族の生活基盤を補償する国の制度です。関係請負人への福利厚生の一環と位置づけ、制度を導入する企業もあります。
※加入対象外地域: 石川県、福井県、島根県、広島県、愛媛県、高知県、沖縄県傘下の一人親方の特別加入を推進しているが、なかなか加入促進が図れない
自動車を運転しようとする時、ほとんどの方は自動車保険に加入すると思います。無保険だと知ったら、不安でその車の運転はできないと思います。車を運転する、すなわち自動車保険なのです。それと同じように、企業で働く労働者は労災保険に加入します。働く労働者、すなわち労災保険となります。
では、一人親方や事業主の方はどうでしょう? 建設業では、労災保険に特別加入することにより、万が一の時でも労働者と同等の補償を受けられるのですが・・・残念ながら、働く一人親方・事業主の方、すなわち労災保険特別加入となっていないのが現実です。
被災リスクの高い建設業で働いている一人親方や事業主の方が労災保険に未加入ということは、無保険の状態で車を運転するのと同様にリスキーなことなのです。
自分が万が一被災して“働けない” “障害が残る” “亡くなる”といった状況になった時、本人と家族が生活していくのにどのくらいの費用が必要か。また、それに備える為には、どういった補償が必要なのかを正しく理解していただくことが必要です。
労災研究所グループは、様々な被災ケースについて、加入者の立場で具体的にシミュレーションしながらわかり易くご説明します。一人親方の方を使用する企業の労災保険特別加入制度の加入促進と、一括加入管理による企業の管理業務を全面的にサポート致します。
 この労災保険の特別加入制度は、被災リスクの高い建設業で働く一人親方である皆さんを救済できる国の制度です。この制度を利用することで、万が一の場合にも国から手厚い補償を受けることができます。
この労災保険の特別加入制度は、被災リスクの高い建設業で働く一人親方である皆さんを救済できる国の制度です。この制度を利用することで、万が一の場合にも国から手厚い補償を受けることができます。
 皆さんが仕事に復帰するまでの期間は、休業補償として皆さんとご家族の生活を支えてくれます。重い障害を受けた場合には、生涯にわたって年金を受け取ることもできます。
皆さんが仕事に復帰するまでの期間は、休業補償として皆さんとご家族の生活を支えてくれます。重い障害を受けた場合には、生涯にわたって年金を受け取ることもできます。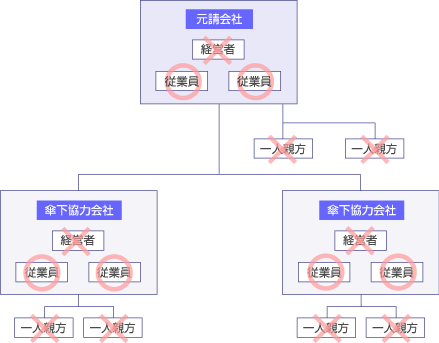
 貴社では、毎年の煩雑な加入確認作業が不要となるばかりか、保険期間中途で退会し、労災保険が使えなくなった人たちを確実に排除することが可能です。
貴社では、毎年の煩雑な加入確認作業が不要となるばかりか、保険期間中途で退会し、労災保険が使えなくなった人たちを確実に排除することが可能です。